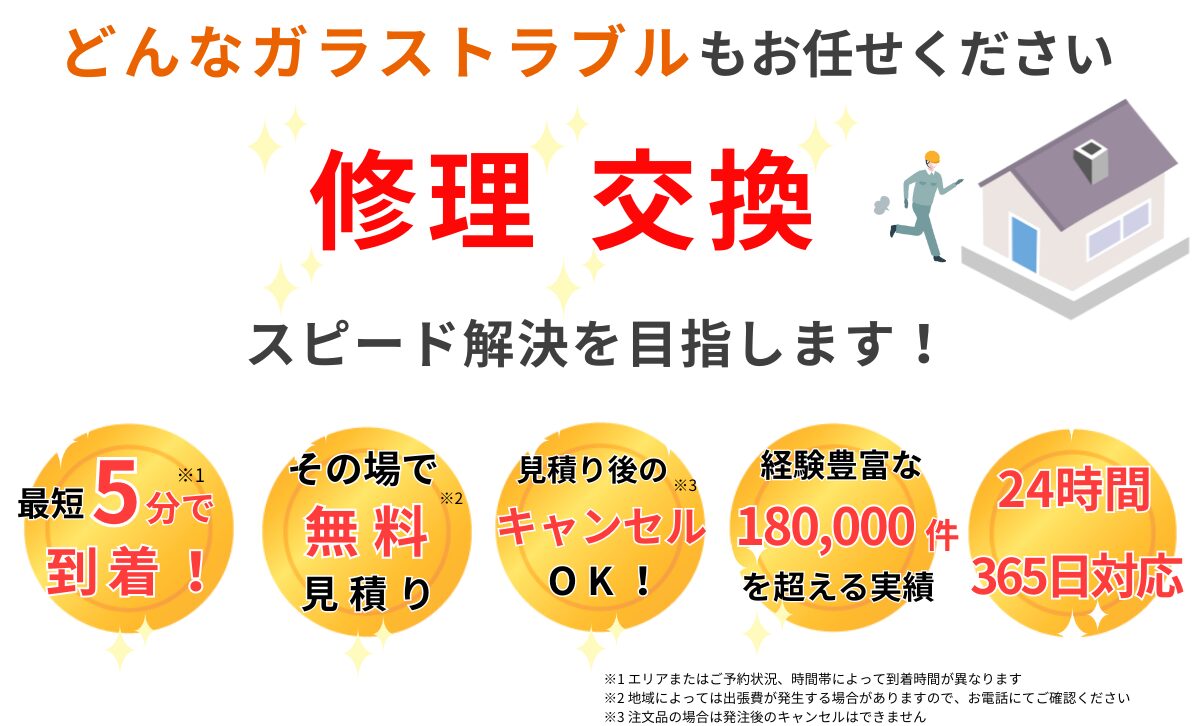「窓ガラスの結露がひどいので、効果的に防止したい」
「拭いてもキリが無い!アパートやマンションの窓の結露対策をしたい!」
窓ガラスの結露に悩む声も多く聞きます。
そこで今回は、すぐにできる13の結露対策をご案内していますので確認してみてください。
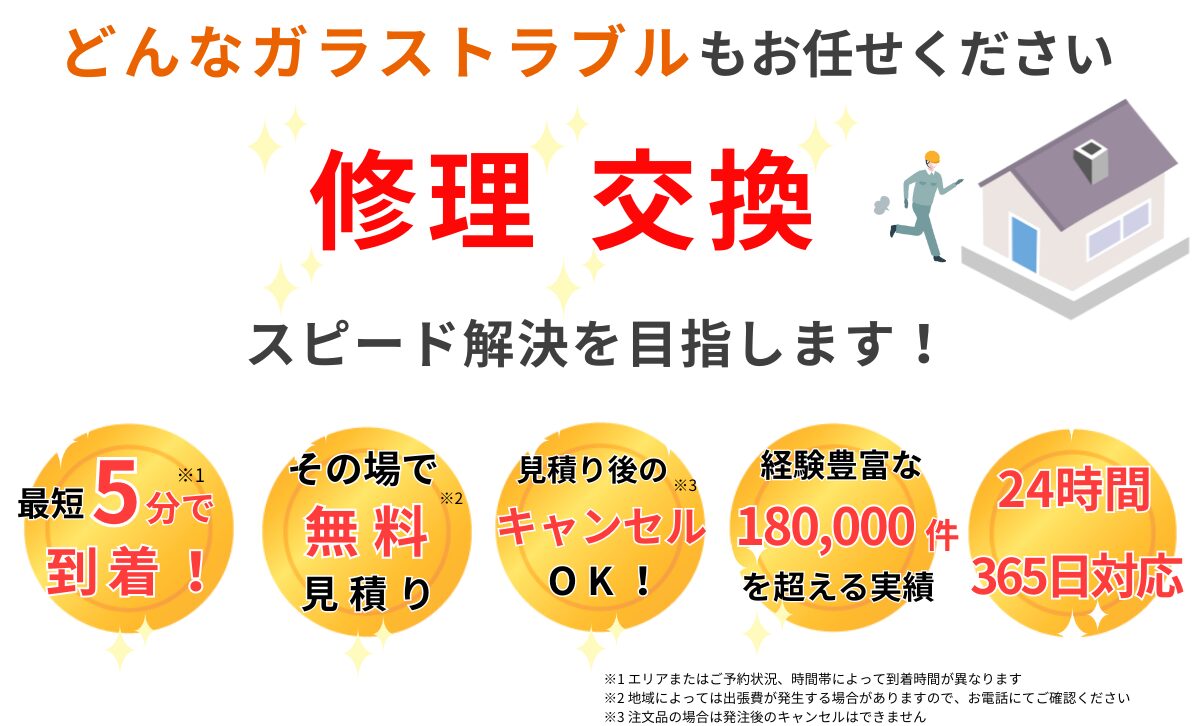
目次
窓ガラスの結露防止のために理解しておくべき3つのポイント
結露には冬型と夏型の2種類ありますが、窓ガラスに水滴が付くのは冬型結露です。
次の情報を把握しておくと、冬型結露への最適な対策が打てるようになります。
結露対策で理解しておくべき3つのポイント
①結露のメカニズムと原因
②結露が起きる温度=露点
③結露防止をしないリスク
それぞれ詳しくご案内していきます。
【ポイント①】窓ガラスの結露のメカニズムと原因
結露のメカニズム
1.空気には水蒸気が含まれている
2.温度が下がるとその水蒸気を維持できる量が減る
3.維持できない水蒸気は凝結(圧縮)されて露(水滴)になる
冬に温まった水蒸気たっぷりの空気が、冬の冷たい窓ガラスに触れることで温度が低下すると、維持できる水蒸気の量が大きく減ります。
空気が水蒸気を維持できなくなると凝結(ぎょうけつ)し、露(つゆ=水滴)に変わり、結露の原因になるのです。

結露する原因は主に以下の3つです。
窓ガラスの結露「3つの原因」
・湿度が高い=空気中の水分量が多い
・外気と室内の温度の差が大きい
・空気の流れが無い
湿気の多い空気が窓の周辺に留まり続けると、空気が冷えて結露になりやすくなります。
アパートやマンションの窓ガラスに結露ができやすいのは、一軒家に比べて窓が少なく湿った空気が留まりやすからです。
【ポイント②】窓ガラスの結露が起こる温度=露点
結露する温度のことを露点(ろてん)といい、温度と湿度で次のように変わります。
・露点の早見表
| 部屋の温度 | 湿度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30% | 40% | 50% | 60% | |
| 30℃ | 10℃ | 15℃ | 18.5℃ | 21.5℃ |
| 25℃ | 6℃ | 10.5℃ | 14℃ | 17℃ |
| 20℃ | 2℃ | 6℃ | 9.5℃ | 13℃ |
| 15℃ | -2℃ | -1℃ | 5℃ | 7.5℃ |
| 10℃ | -6℃ | -2.6℃ | 0℃ | 2.5℃ |
例えば、部屋の温度が25℃で、湿度が40%の場合、外の温度が10.5℃になると結露が発生します。
一般的に快適な湿度とされているのは40%~60%です。

この快適な湿度の部屋の温度を25℃にすると、外気が10.5℃~約17℃で結露します。
明け方の気温が10℃を切る秋から春先までに窓ガラスが結露しやすいのはこのためです。
【ポイント③】窓ガラスの結露防止・対策をしないリスク
窓ガラスの結露防止・対策をしないリスクについても確認しておきましょう。
結露防止・対策をしないリスク
・カビが発生する
・ダニが発生する
・人体に悪影響がある
・住まいを劣化させる

部屋のカビやダニが原因でシックハウス症候群や真菌症、アレルギーが発症することがあります。
この他、窓周辺の床や壁にシミができて痛んだり、腐ったりしてしまうこともあるため、早めの対策が必要です。
窓ガラスの結露対策&防止法13選!おすすめの防ぐ方法は…
・13の結露防止・対策(価格の安い順)
| 対策方法 | 費用 | 効果 |
| ①換気をする | 0円 | △ |
| ②こまめに拭き取る | 0円 | △ |
| ③吸水テープを使う | 100円~ | △ |
| ④断熱シートを使う | 100円~1,000円 | △ |
| ⑤除湿剤を使う | 500円~ | △ |
| ⑥調湿機能のある壁紙を使う | 600円~ | △ |
| ⑦結露防止スプレーを使う | 1,500円前後 | △ |
| ⑧サーキュレーターを使う | 3,000円~30,000円 | △ |
| ⑨窓用ヒーターを使う | 12,000円~35,000円 | △ |
| ⑩水蒸気の出ない暖房機器に替える | 2,900円~260,000円 | 〇 |
| ⑪除湿器を使う | 20,000円~90,000円 | 〇 |
| ⑫複層ガラスに交換する | 41,000円~210,000円 | ◎ |
| ⑬二重窓(内窓・二重サッシ)にする | 40,000円~400,000円 | ◎ |
結露防止の効果が高く、手間がかからないことから、結露対策には複層ガラスへの交換がおすすめです。
他にもお金がかからない対策を1つずつ詳しくご紹介します。
【結露対策①】換気をする

窓ガラスの結露の原因の1つは、部屋の空気が動かないことであり、換気をすることで解消できます。
費用がほぼゼロでできるため、ほとんどの方が一度は実践されますが、確実な効果が見込めるわけではありません。
換気しても翌朝には「窓が結露していた…」などということもあります。
【結露対策②】こまめに拭き取る

「窓ガラスの結露がひどいので毎日ふき取ってる」という方もいるはずです。
しかし、カビやダニの発生は防いだり、遅らせたりすることができるものの、窓の結露自体は防げません。
【結露対策③】吸水テープを使う
吸水テープのメリット
・手軽にできる
・100均でも購入できる
・かわいい柄などもある
吸水テープのデメリット
・結露は発生する
・カビが生える
・すぐに剥がれる
・テープの存在感が気になる
吸水テープは、窓の下部に貼って結露を吸収させるテープです。
結露を防ぐアイテムではありませんが、発生した結露を吸収し、床などに垂れるのを防ぎます。
剥がれにくくするために、事前に貼る場所の汚れを拭き取り乾いた状態にしておくようにしてください。
吸水テープ自体のカビが心配な方は抗菌タイプを選ぶとよいでしょう。
【結露対策④】断熱シートを使う
断熱シートのメリット
・断熱効果で節約になる
・暑さも防げる
・目隠し効果もある
断熱シートのデメリット
・見た目が変わる
・剥がれてくる
・貼るのにコツがいる
断熱シートは窓に貼り付けて窓から伝わる冷たい空気を防ぎます。
結露になる原因の1つである、外気と室内の温度の差が大きい場合の対策です。
梱包材のようなプチプチタイプ、曇りガラス風や柄入りの薄手タイプなど好みによって選べます。
断熱シートを選ぶポイント
・100均でも購入可能
・ネットショップやホムセンでは1,000円前後
貼る前に窓の汚れを拭き取り、霧吹きなどで窓に水をスプレーして貼り付けて使用します。
【結露対策⑤】除湿剤を使う
除草剤を使うメリット
・置くだけなので簡単
・乾燥させて繰り返し使える
除草剤を使うデメリット
・これだけでは部屋全体の湿気を取れない
結露する窓の下に置き、湿度が高い場合の対策として使います。
窓周辺の湿気を吸ってくれますが、部屋全体の湿気を取るには十分ではないので、他の対策と併用をしてください。
繰り返し使える結露専用の除湿剤にはシリカゲルB型のもの、珪藻土(けいそうど)でできたものがあります。
除湿剤を選ぶポイント
・シリカゲルは500円前後~
・珪藻土は1000円~
シリカゲルの物は細長い形状で窓下にフィットする形です。
珪藻土制のものはタイル状やオブジェの形のものがあり、見た目がスタイリッシュな点が魅力です。
【結露対策⑥】調湿機能のある壁紙を使う
除湿機能のある壁紙を使うメリット
・見た目を変えなくてもOK
・柄を選ぶ楽しさがある
除湿機能のある壁紙を使うデメリット
・DIY難易度が高め
・これだけでは効果が薄い
・賃貸の場合は許可が必要
マンションやアパートの場合、コンクリートが下地では効果がなく、管理者の許可が必要です。
調湿機能のある壁紙を選ぶポイント
・価格は600円~
・3種類ある
・防カビ効果もあるものを選ぶ
壁紙の金額はそこまで高額ではありません。
| 壁紙の種類 | 費用 |
|---|---|
| 貼って剥がせる壁紙 | 10m 1,900円~ |
| 調湿タイル(30×30㎝) | 1枚600円~ |
| 珪藻土壁材3kg(使用の目安2.5~3.5㎡) | 3,000円~ |
ただし、壁の範囲が広ければ相応の費用がかかります。
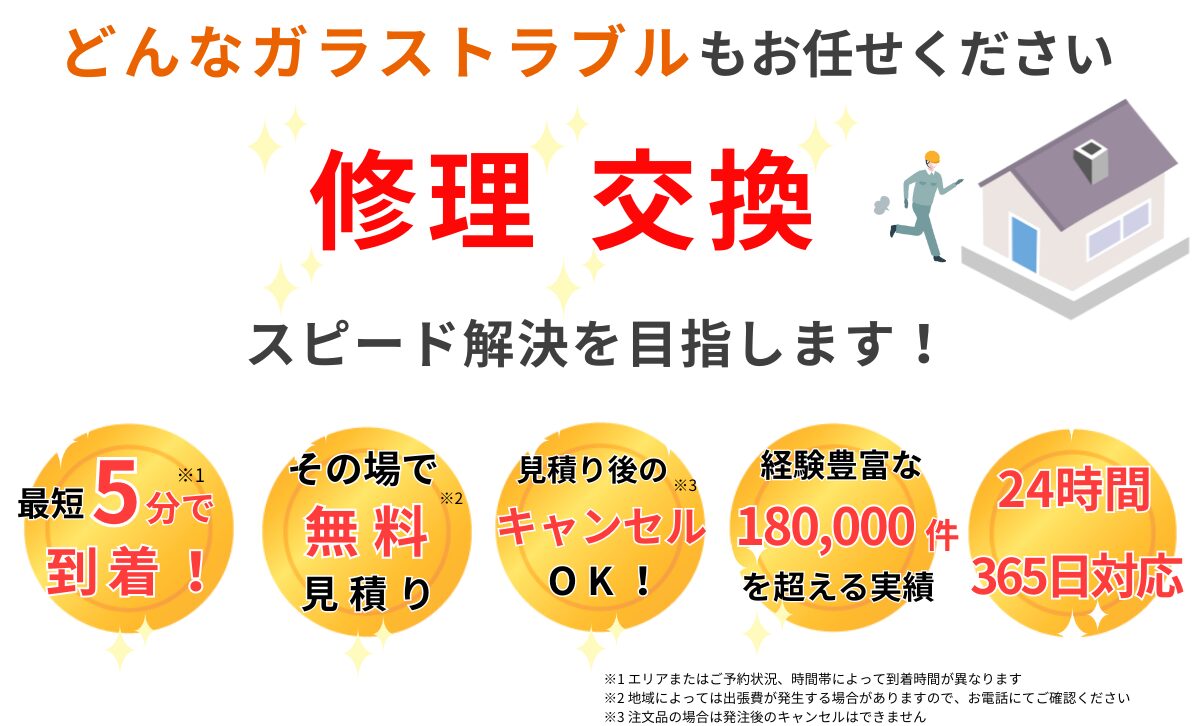
【結露対策⑦】結露防止スプレーを使う
結露防止スプレーのメリット
・見た目が変わらない
・手軽にできる
結露防止スプレーのデメリット
・これだけでは効果が薄い
簡単で便利ですが「これだけでは効果が無かった」という口コミ・レビューが多いので、他の対策と併用をしてください。
結露防止スプレーを選ぶポイント
・価格は1,500円前後
・拭き取りが必要なものと不要なものがある
・防カビ効果もあるものを選ぶ
スプレー後、拭き取りが必要で仕上がりが綺麗なものと、拭き取り不要でより手軽なものがあります。
防カビ効果があるかどうかも選ぶ時のポイントです。
【結露対策⑧】サーキュレーターを使う
サーキュレーターを使うメリット
・暖房効率(冷房効率)も上げてくれる
・比較的手ごろな価格
サーキュレーターを使うデメリット
・正しく使わなければ効果が薄い
・音がうるさいことがある
部屋の空気を循環させることで結露を生じにくくすることが可能です。
サーキュレーターを選ぶポイント
・価格の相場は3,000円~30,000円
・音の小ささ、お手入れのしやすさも考える
・用途に合わせた正しい使い方が大事
サーキュレーターを使用する際は、厚手のカーテンが窓への空気の流れを塞いでしまうことがあるため、寒くてもカーテンは開けておいてください。
【結露対策⑨】窓用ヒーターを使う
窓用ヒーターを使うメリット
・暖房効率(冷房効率)も上げてくれる
・置くだけ簡単
・底冷えの軽減にも
窓用ヒーターを使うデメリット
・電気代がかかる
・熱くなりすぎたら危険なことも
窓の下に置くことで、暖かな空気の流れを発生させ、窓からの冷気をシャットアウトします。
窓用ヒーターを選ぶポイント
・定尺タイプの相場は12,000円~22,000円程度
・伸縮タイプの相場は30,000円前後
・電気代は時間当たり1~3円程度
・部屋全体は暖かくならない
・安全のためカーテンに触れさせない
長さを変えられないタイプのヒーターは12,000円~程度で購入可能ですが、窓の長さに合わせて伸縮できるタイプは3万円前後と少し高額になります。
これだけで部屋全体を温めることはできませんが、窓からの冷気を防いで暖房効率を上げる効果が期待できます。
【結露対策⑩】水蒸気の出ない暖房機器に替える
水蒸気の出ない暖房機器に替えるメリット
・灯油やガス代がかからなくなる
・安全性が上がる
水蒸気の出ない暖房機器に替えるデメリット
・電気代がかかる
・部屋が乾燥する
・エアコンの場合は設置費もかかる
水蒸気が出ない暖房機器とは、電気ストーブやエアコンのことです。
ただ空気が乾燥しているため、加湿器を使って湿度をコントロールする必要があります。
なお、石油ストーブやガスファンヒーターなど灯油やガスを燃料とする暖房機器は水蒸気を発生させますので、結露がひどい場合は使用しないようにしてください。
暖房機器を選ぶポイント
・電気ストーブの価格は小型のものは2,900円~
・エアコンは商品代と取り付け費がかかる
小型の電気ストーブは比較的安価なものからあり買い替えの負担も少なく抑えられます。
【結露対策⑪】除湿器を使う
除湿器を使うメリット
・湿度をコントロールできる
・持ち運びしやすい
除湿器を使うデメリット
・加湿器を使っている人は使えない
・電気代がかかる
空気中の水分を取り除くことで結露防止に効果があります。
除湿器を選ぶポイント
・結露対策にはデシカント式がおすすめ
・デシカント式除湿器の相場は20,000円~30,000円
・電気代は8~12円/時間
冬の窓の除湿には、寒い時期でも機能が低下しないのデシカント式がおすすめです。
【結露対策⑫】複層ガラスに交換する
複層ガラスに交換するメリット
・防音効果もアップする
・見た目が変わらない
・補助金がある
複層ガラスに交換するデメリット
・ガラス代が高い
・樹脂サッシにする必要がある
・DIY難易度が高い
複層ガラスは冬の冷たい空気を通しにくく、窓を部屋の温度に近い状態に保つため、結露ができにくくなります。
一度設置すればいいだけですので、もっともおすすめの窓ガラスの結露対策です。
なお、ガラスが2枚のものをペアガラス、3枚のものをトリプルガラスと呼びます。

トリプルガラスは冬の寒さが特に厳しい北海道や東北、北陸で利用されている断熱効果が高いガラスです。
断熱効果はガラスの種類やサイズ、枚数、層に入れる気体の種類などにより金額が変わります。
| ガラスの種類 | 価格(90cmx90cm) |
|---|---|
| ペアガラス(標準) | 15,000円~35,000円 |
| Low-Eスリムペア | 50,000円~100,000円 |
| トリプルガラス | 50,000円~100,000円 |
| 真空ペアガラス | 80,000円~150,000円 |
工賃は26,000円~58,000円程度、金額は41,000円~208,000円です。
既存のサッシがアルミの場合は樹脂サッシに換える必要があり、断熱窓に換える場合補助金で一部の費用を賄えるため利用を検討してみてください。
ガラス交換の業者は、次のようなポイントで選ぶと良いです。
交換業者を選ぶポイント
・支払い方法が豊富
・アフターフォローがある
・見積もり後に追加料金が無い
【結露対策⑬】二重窓(内窓・二重サッシ)にする
二重窓(内窓・二重サッシ)にするメリット
・断熱効果が高い
・防音効果がある
・防犯効果が高い
・補助金がある
二重窓(内窓・二重サッシ)にするデメリット
・相応の費用がかかる
・窓の開閉に手間がかかる
・掃除の手間が増える
・既存の窓の結露対策は不十分
・見た目が変わる
二重窓とは、既存の窓の内側にもう1つ窓を作る方法です。
交換業者を選ぶポイント
・複数業者に見積もりを依頼する
・ホームページでサービス内容を見る
二重窓へのリフォーム代は10万~です。
業者や作業内容、状況によって費用が変わります。
アパート・マンションの窓ガラスの結露対策「3つの注意点」
アマパンの窓ガラスの結露対策「3つの注意点」
【注意点①】対策しないと退去時に修繕費を請求される
【注意点②】結露しやすい地域・アマパンの可能性がある
【注意点③】管理者の許可が必要な場合がある
アパート・マンションの窓ガラスが結露する場合は、最適な行動を取れるように、3つのことを知っておいてください。
【注意点①】対策しないと退去時に修繕費を請求される

賃貸アパートや賃貸マンションで窓の結露を放置していて、カビが生えてしまった場合、退去時に修繕費を請求されてしまうことがあります。
法律上、必要な対策や掃除をおこなわずカビが生えた場合、借りた側が修繕費を負担しなければならないからです。
換気と除湿だけでなく、結露ができたら拭き取るなどの対策は求められます。
【注意点②】結露しやすい地域・住宅の可能性がある

2003年(平成15年)7月に改正された建築基準法で、24時間換気システムで空気の入れ替えを行うことが義務になっています。
それ以降の建物では、24時間換気システムがあるため、多少、結露防止の効果はあると考えられます。
それでも結露する場合は、結露しやすい地域、アパートやマンションそのものに原因があるかもしれません。
先にご案内した13の方法を積極的に試してみてください。
【注意点③】管理者の許可が必要な場合がある

13の結露対策のうち、実施する場合は管理者に事前に確認することをおすすめします。
例えば、壁を調湿機能のある壁紙に変える場合、管理者の許可が必要です。
なお、コンクリートは通気しないため、コンクリートが下地となっているアパートやマンションの場合、壁紙の結露防止効果はありません。
窓ガラスの結露対策やアパートの結露防止のまとめ
このページのまとめ
・窓ガラスの結露対策・防止法は13ある
・おすすめなのは効果の高い複層ガラスへの交換
・アパート・マンションの結露対策には3つの注意点がある
窓ガラスの結露への対策方法、防止法は13つあります。
対策をしても結露する場合や結露がひどい場合は、断熱効果が高く、結露がしにくい複層ガラスへの交換を検討してみてください。
アパートやマンションの場合は管理者の許可が必要な場合もあるため、確認をしてから結露防止対策を行うようにしましょう。